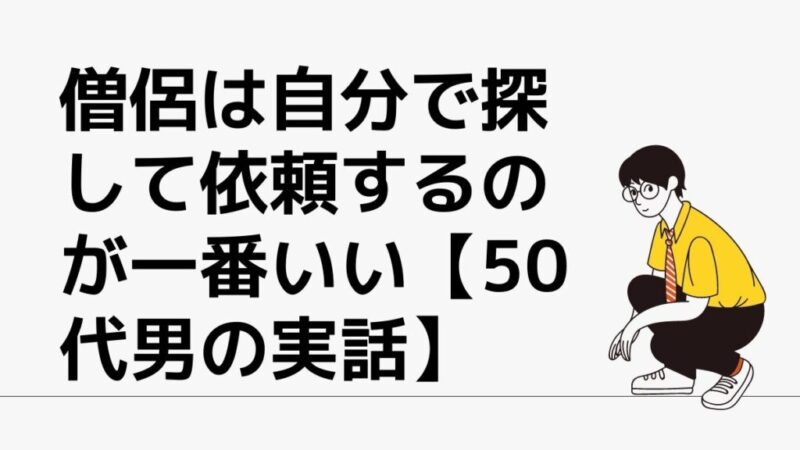はじめに 終活は人生の不安を減らす活動
「終活」という言葉は、『週刊朝日』の造語であるといわれています。2009年の8月から12月にかけて、『週刊朝日』に「現代終活事情」という特集が連載されました。
葬儀社選びから葬儀の見積もり、葬儀と埋葬法の種類や墓地・墓石の選び方など、納得のゆく葬儀をしたい人に役立つ情報が紹介された内容は、当時の週刊誌として画期的な試みだったようです。
葬儀体験者と業者双方の声を交えつつ、現代の葬儀のあり方を嘘偽りなく紹介した記事は、何より消費者側の視点をふまえたものでした。
悔いの残らぬ葬儀をしたい。そう願う誰もが具体的に知っておきたい費用の面など、葬儀にまつわる金銭トラブルを避けるための知恵も提示されており、遺言についての回も組まれています。
やがて来る自分の最期、あるいは身近な人の最期に向けて十全に備えをするための手がかりとして、「現代終活事情」は多くの人が参照するところとなったのでした。
死への準備が終活の本質
葬儀の実際を考えることが大切
この「現代終活事情」の記事は、葬儀の実際を知りたいと願う人々のニーズにうまくこたえるものとなりました。と同時に、葬儀への事前準備を読者に促し、人生の終焉を自覚させる役割をも担ったようです。それまでは無意識裡に抱きながらも明るみには出てこなかった人々の、死に対する意識を引き出した、ともいえるでしょうか。いつかは必ず訪れる死。免れ得ないその事実は、誰もが漠然とは思い描きながらも、なるべくなら考えたくはない将来でしょう。
人生を見つめ直す時間、死への準備は心の準備
死がタブー視されている世間にあっては、どうしても負のイメージがつきまといます。まして、死にまつわる具体的な身の処し方、葬儀やお墓について計画をするなどに至っては、あまりに不吉で陰惨な所為だと感じるのは当然かもしれません。しかし、心の一方では、人生の最期に関する諸々が気にかかっている……。「終活」という言葉はそのようなわだかまりを払拭し、「死への準備」が、公の場でみんなに認められるきっかけを作った、といえるようです。
ビジネスと結びついた終活
終活セミナーとエンディングノート
「終活」が流布してからは、「終活」に関する書籍が次々と発行され、葬儀業者をはじめとして遺品整理業者や高齢者住宅を扱う業者など、様々な業界の間にも「終活」の語は浸透してゆきます。今や行政書士、司法書士が催すセミナーの名に「終活」が付かないことはありません。2011年11月には映画「エンディングノート」(死を迎えた後の身辺処理や葬儀の希望、家族への伝言などを書き留めておくノート)が公開され、テレビでも「終活」を取り上げる番組が放送されはじめました。
実際の活動は人生の振り返り
死の事前準備は、ようやく私達に認知されたといえましょう。ただ、「終活」が市民権を得たとはいえ、その実態ははっきりとしていないのではないでしょうか。「終活」というと、「永代供養」「家族葬」「直葬」「自然葬」「散骨」「遺言」「遺書」「エンディングノート」……など、たくさんのキーワードが浮かびます。たった2文字の「終活」に多くの事柄が附随しています。あなたがもし、「終活」について真剣に考えてみようとする場合、それぞれの事柄をバラバラにあたると混乱するばかりになるかもしれません。が、おおもとの「終活」の思想を知っておけば、事に際しての失敗は少なくなります。また、「終活」に対して賛成するにせよ、反対するにせよ、その実質を少しでも把握しておくことは私達にとって有益である筈です。
人生のエンディングを決めておく
【終活】「終わりの活動」の略。人生のエンディングを自分らしく迎えること。また、その実現を生前から考え、準備すること。(『わたしの葬式 自分のお墓』)
「現代終活事情」を再編して出版された『わたしの葬式 自分のお墓』の冒頭です。ずばり「終活」の定義が述べられています。「人生のエンディング」とは、言い換えれば〈死ぬこと〉。暗くて重苦しいイメージの〈死〉が、「エンディング」という言葉に置き換えられて、どことなく軽やかで清々しく感じられます。自分に相応しい死を実現するために準備をする、という点もポジティブです。目を背けるのでもなければ、抗うのでもない、死に対する前向きな姿勢がそこにはあります。一見、死の準備とは不穏な響きです。
生きるために終活をする
ともすれば自死と見紛う人もいるかもしれませんが、〈生〉に重きを置く点において「終活」と自死は異なります。後者の場合、残された人たちは故人に裏切られた気持ちを抱くことが多いようですが、「終活」とは、家族を含む身の回りの人たちと関わっている現実=〈生〉を見つめ直すことから始まります。具体的に関係を取り持っている人との関係をふまえたうえで、自分にも、他人にも納得のゆく最期に向けた備えをする。「終活」は、自分と他人との折り合いをつける最後の機会であるともいえるのです。
終活で自分だけの死ではないことを意識する
自分らしいを探す必要はない
自分らしい最期を準備しようとおもうとき、自分を取り巻く現実を無視するわけにはいきません。家庭を持っている人であれば、家族があなたの死を弔うことになります。死後、葬儀と埋葬はもちろんのこと所持金や所有物など故人にまつわる諸々を整理するのは、後に残された人です。葬儀は故人を偲ぶための生者の集まりであり、埋葬も他人の手によります。
終活をしても、結局は残された家族がするのだから考えすぎない
自分の計画する「エンディング」がどんなに素晴らしい構想であろうと、家族をはじめとする他人の協力なしには、その実現は難しいに違いありません。つまり、あなたの死は自分だけのものではなく、他人のものでもあるのではないでしょうか。『わたしの葬式 自お分のお墓』の監修を務めた市川愛は、著書『「終活」のすすめ』でこう述べています。
誰もが遺される家族に迷惑をかけたいなどとは思っていません。しかし、心ならずもそのお葬式で後悔してしまう家族が後を絶たない今、あなた自身ができることをしておくのが最良の選択なのではないでしょうか。「残される家族に迷惑をかけたくない」その思いやりを形にできるのが「終活」なのです。
〈略〉また、終活とはお葬式の準備に限ったことではありません。これは、あなたがこれからの人生を活きいきと、あなたらしく過ごしていくという「決意表明」なのです。
終活の意味、それは、ご家族への思いやりと、あなたらしさを両立することです。 (市川愛『「終活」のすすめ』)
自分を再発見することに終活の意味がある
「あなた自身ができることをしておく」ためには、まず人との関わりの中に生きている自分を再発見することが出発点となる筈です。おのずとこれまで歩んだ人生を振り返ることにもなるでしょう。過去から現在に至るまでの過程を想い起こせば、総決算としての最期が見えてくるかもしれません。そうして残された生の時間を大切にして、充実させることが「終活」の目的であるといえます。死を前向きに受けとめて、残された時間を大切に、生きる。自分のため、人のための準備をする。大雑把ではありますが、以上が「終活」のテーマといえるのではないでしょうか。
正しい死に方はない
死は1度しか訪れないから終活が人生で大切
「終活」という語は親しみすく、便利な言葉です。ただ、安易な言葉遣いだけに、少なからず疑問を感じる人もいるのではないでしょうか。人生の最後にかかわることを、「終活」で十把一絡げにしてしまいがちなのではないか。厳粛である筈の死に対して、余りにも形式的なのではないか……。
「就活」や「婚活」の派生語である事実に眉をひそめる方もいるでしょう。そもそも人生の大切な節目である就職や結婚を、活動として割り切るのも不自然であるのに、よりによって「終活」だなんて、と。
確かにそうかもしれません。就職、結婚は人によっては繰り返すことができるでしょうが、死は人生の最後である以上、取り返しのつかない一度きりの出来事です。いつ、どんな場所で訪れるか予測も難しい、死。
そんな厳粛である死を「終活」という一言で見積もるのは人間の傲慢では、と感じるのは当然なのかもしれません。ただ、「終活」が普及する今日までの日本で、正しく死が実現されていたのかといえば、果たしてどうでしょうか。
ブームではない終活、自分にとっての解を見つける。
正しい死に方というと変なようですが、「終活」という言葉に違和感を覚える以上は、何かしら理想的な死のイメージがある筈です。転がるように果てたい。流れるように尽きたい……。
しかし、多くの人が、病院のベッドで最期を迎える可能性の高いのが現実でしょう。理想はどうあれ、死のかたちは画一化されています。逆にいうと、このような死の画一化のゆえにこそ、その中で各々が独自性のある死を持とうと欲し、「終活」ブームの到来となったのかもしれません。そう考えると、「終活」ブームの背後には、現代に生きる私達のあり方がみえてくるようです。死の在り方が変容するにつれて、死に対する意識が変わりつつある私達のあり方です。
『葬式は、要らない』で「葬式無用論」を唱える島田裕巳は、日本独自の葬式仏教を考察しながら、内実の疑わしいこれまでの葬儀形式を批評する中で、死のかたちの変容についても言及しています。
〈略〉村落共同体の力が衰え、もう一つの共同体である家族の役割が低下して、共同体の行事としての葬式の意味は変わった。死はあくまで個人のものとなり、共同体のものではなくなった。そうなれば、葬式の必要性は薄れていく。
葬式無用の流れは、もっぱら葬式を担うことでその存在意義を示してきた仏教、いわゆる「葬式仏教」を衰退させることにもつながっていく。葬式仏教の成立は、近世のはじめ、今から400年ほど前のことだが、その基盤が崩れつつある。
(島田裕巳『葬式は、要らない』